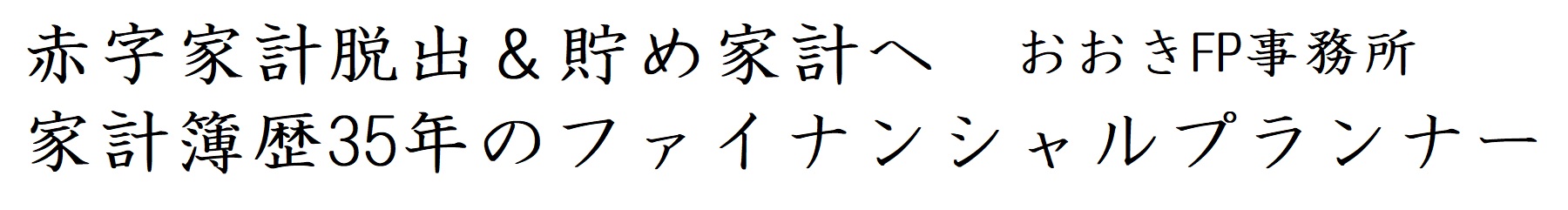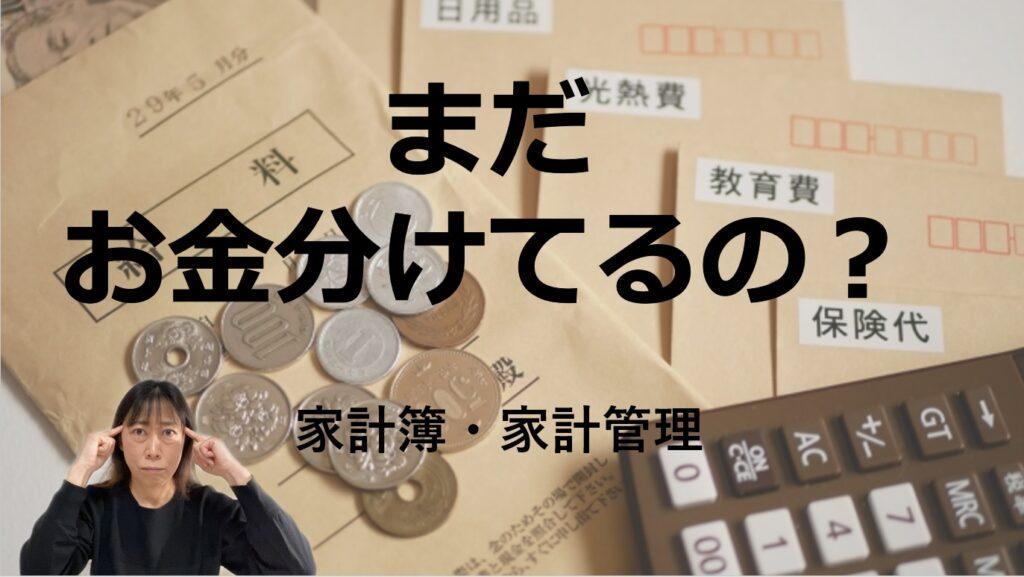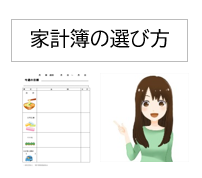袋分け家計簿の成功のコツはお金の分け方。金種分けだけでは成功しない理由をFPが解説します
袋分け家計管理とやりくり費
家計簿歴(もうすぐ)37年の家計簿FP(ファイナンシャルプランナー)おおきです。
家計簿の選び方は家計簿生活始めの一歩です。
しかし、どの家計簿を使えばいいのか?悩みどころですよね。
そこで、今回は袋分け家計簿第2回目です。
袋分け家計簿を始めてみたい方、袋分け家計簿を挫折した方はぜひ第1回~第3回も併せてご覧ください。
袋分け家計簿成功のコツが掴めますよ。
 ※袋分け家計簿の使い方はこちらも合わせてお読みください。
※袋分け家計簿の使い方はこちらも合わせてお読みください。
袋分け家計簿で挫折する人が多い理由と対処方法
◆第1回袋分け家計簿はお金が貯まらない
目 次
袋分け家計簿に関してYouTubeでも配信しています。
こちらは袋分け家計簿で挫折した人向けの内容です。
クリックしてぜひご視聴ください。
袋分け家計管理の問題点
前回触れましたが、そもそも袋分け家計管理の問題点はやりくり費が適正かどうかという部分にあります。
週ごとや費目ごと袋に分けた金額が適正でなければ成り立たないのです。
週単位で袋分け管理するとしましょう。
仮に、やりくり費を月5万円と設定します。
一週間当たり1万円ですよね。
しかし、お金が足りなくなり次の週の予算を拝借してしまうことの繰り返し。
週ごとにお金を振り分けても足りなくなれば次の封筒に手を伸ばしてしまいます。
結局、第三週ごろには第五週分の封筒が空になってしまいます。
どうにか節約してお金を足らそうとするのですが、なかなかうまくいきません。
袋分け家計簿が上手くいかない理由
このようなケースの場合に考えられることは、そもそものやりくり費の額が適正でないことです。
月のやりくり費5万円をどのように決定しているかがポイントです。
▶節約しても家計が苦しい
▶節約しても赤字が解消できない
このような家計は、やりくり費に配分した金額がもともと足りないのです。
ということは、やりくり費に配分する金額が適正かどうか見極める必要がありますよね。
ほとんどの人が次のようにやりくり費を決めています。
収入-諸々の支払い(住居費などの固定費、光熱費などの変動費)。
その残額がやりくり費に充てられる金額です。
もろもろ支払って、その残りで生活しよう。
このように決まった金額がやりくり費です。

金種分けしても袋分け家計簿が成功しない理由
やりくり費で賄う支出は、食費や日用品など毎日の生活で必要な品々です。
この部分だけでなんとか家計のつじつまを合わせようとして行うのが節約ですよね。
しかし、どう頑張っても毎月8万円が必要な家計なのに、5万円しか配分できなければどうでしょうか。
スタート前から3万円足りないのですから、いくら頑張って節約を試みても家計は楽になりません。
袋分け家計簿挫折行為である次週の袋から拝借。
もともとお金が足りないのだとしたら、仕方がないといえますよね。
いくら金種分けしても袋分け家計簿が成功しない理由はここにあります。
節約云々ではありません。
この記事は家計簿インストラクター講座のサイトで書いています。
ご参考になさってください。
フランスの家計管理支援も家計簿が重要アイテム
袋分け家計簿のデメリットが表面化しない家計
一方、同じように収入から諸々差し引いてやりくり費を割り当てても、お金が余る家計も出てきます。
毎月8万円必要な家計なのに、12万円配分できるようなケースです。
割り当てた時点で4万円余裕があるのです。
さらに節約を併用すれば、家計は楽でしょう。
このような家計は、週ごとに分けた袋にお金が残るので、次週の予算に手を付けることがありません。
適正なやりくり費を算出しなくても、家計が賄えてしまう家計ですね。
袋分けで管理するわが家のやりくり費を把握する
 袋分け家計簿と記帳のコツはこちらをご参考にしてください
袋分け家計簿と記帳のコツはこちらをご参考にしてください
家計簿を成功させるコツ
◆第3回袋分け家計簿で貯金成功する記帳方法のコツをFPが解説
今見てきたように、袋分け家計管理の成功には、袋に分ける金額と実際に必要な金額とが大きく関連してきます。
割り当てる金額は、適正なやりくり費であることが大事です。
やりくり費を算出せずに袋分け家計簿を利用する場合、予算が多い分には不具合は表面化しません。
しかし、そもそも足りない分には、この袋分け家計管理方法は全く機能しないのです。
ここで問題になるのが、適正なやりくり費をどう算出するのか?でしょう。
これは、家計簿を3カ月程度連続してつけて確認するしかありません。
家計簿でわが家の支出を把握する
ここで家計簿が登場します。
一カ月にいくら使っているのかを記入してみましょう。
三カ月程度続ければだいたい見えてきます。
そのうえで、やりくり費に配分していた金額と比べてみてください。
なんとかなりそうでしょうか。
それとも、そもそも配分額が不適正であったでしょうか。
袋分け家計簿は適正なやりくり費を算出してから始める
袋分け家計簿は配分した予算額が不適正であれば機能しません。
そのため、いきなり袋分け家計簿で家計管理を始めることは無謀です。
家計簿初心者さんや家計管理の苦手な人には適さないといえるでしょう。
わが家の予算配分がきちんと把握できている上級者さん向きのアイテムなのです。
いきなり袋分け家計簿をスタートする前に、まずは、わが家の予算をしっかりと算出してみましょう。
また、家計簿にどう取り組んでいいのか迷う初心者は、講座で学ぶのもオススメです。
下記の家計簿講座では、家計簿の書き方や家計管理の基本が一通り学べます。
家計簿は習う時代です。
サクッと基本を身に付けて貯め家計を作りたいと思われましたら、ぜひご活用ください。
FPおおき
1級ファイナンシャルプランニング技能士
家計簿歴36年の家計簿FP(ファイナンシャルプランナー)